紹介論文
今回紹介する論文はHow Do LLMs Use Their Depth?という論文です。
この論文を一言でまとめると
LLMはどのように深さを利用して予測を行うのか?本記事では、LLMの層ごとの予測ダイナミクスを詳細に分析し、初期段階での推測から文脈理解による洗練までのプロセスを解説します。LLMの内部動作を理解し、より効率的なモデル開発に繋げましょう。
イントロダクション:LLMの深さに迫る
大規模言語モデル(LLM)は、その目覚ましい性能で様々なタスクをこなせるようになりました。しかし、その内部で一体何が起きているのか、LLMはその深さをどのように活用しているのでしょうか?
本記事では、LLMの層ごとの予測ダイナミクスを詳細に分析した論文 “How Do LLMs Use Their Depth?” を元に、LLMがどのように深さを利用して予測を行うのかを解説します。
具体的には、以下の疑問に答えることを目指します。
* LLMは推論中に中間表現をどのように利用しているのか?
* 層ごとにどのように予測に到達するのか?
* 特定のトークン予測は常に最終層で計算されるのか?
* モデルは予測可能なトークンを早期に決定し、単純に伝播するのか?
これらの疑問を解き明かすことで、LLMの内部計算をより深く理解し、計算を動的に使用できる、より効率的なLLMを構築するための洞察を得ることができます。
本記事を読むことで、あなたは以下の知識を得られます。
1. LLMの層ごとの計算における「Guess-then-Refine」フレームワークの理解
2. 品詞、事実想起、選択肢タスクにおけるLLMの深さの使い分けに関する事例研究
3. LLMの初期段階での統計的推測と、文脈情報の蓄積による推測の洗練プロセスの理解
4. より効率的なLLM開発に向けた洞察
さあ、LLMの深層学習戦略を理解する旅に出かけましょう!
Guess-then-Refine:LLMの予測フレームワーク
大規模言語モデル(LLM)は、複雑なタスクをこなすために、内部でどのような戦略を用いているのでしょうか?本セクションでは、LLMの予測プロセスを理解するための重要なフレームワークである“Guess-then-Refine”戦略について解説します。結論から言うと、LLMは初期の層で大まかな「推測」を行い、その後の層で文脈情報を加味して洗練させていく、という構造的なアプローチを取っています。
Guess-then-Refineフレームワークとは
“Guess-then-Refine”フレームワークは、LLMが予測を行う際に、以下のステップを踏むことを示唆しています。
- 初期層での推測 (Guessing):LLMは、入力されたテキストのごく一部の情報に基づいて、次に来る可能性の高いトークンを予測します。この段階では、文脈情報が不足しているため、高頻度で出現するトークン(例えば、「the」や「a」など)が選択されやすい傾向があります。これは、まるでサイコロを振るように、統計的な確率に基づいて「当たり」を狙う行為に似ています。
- 深層での洗練 (Refining):モデルがより深い層に進むにつれて、より多くの文脈情報を処理できるようになります。その結果、初期の層で推測されたトークンは、文脈的に適切なトークンへと洗練されていきます。例えば、初期の層で「the」と推測されたトークンが、文脈に応じて「dog」や「cat」などの具体的な名詞に置き換えられることがあります。
このフレームワークの興味深い点は、初期の層で行われた推測が、必ずしも最終的な予測に繋がらないことです。実際、研究によれば、初期の層で高頻度トークンとして予測されたものでも、70%以上が後の層で洗練されることがわかっています。これは、LLMが単に初期の推測を鵜呑みにするのではなく、継続的に情報を更新し、より適切な予測を目指していることを示唆しています。
頻度に基づく予測の開始 (Frequency-Conditioned Onset)
LLMが初期の層で高頻度トークンを推測する傾向は、“Frequency-Conditioned Onset”と呼ばれています。これは、LLMが初期の層では、まるでコーパスの統計情報に頼るかのように、出現頻度の高いトークンを優先的に選択するという現象です。しかし、これは単なる統計的な偏りではありません。後の層で大幅な洗練が行われることを考えると、初期の層での高頻度トークンの選択は、あくまでも「推測」の段階に過ぎないと言えるでしょう。
TunedLensによる検証:初期層の「推測」を可視化する
この”Guess-then-Refine”フレームワークを裏付けるために、研究ではTunedLensというツールが活用されています。TunedLensは、LLMの内部表現をより忠実に可視化するための技術であり、特に初期の層におけるトークン予測パターンを詳細に分析することができます。TunedLensを用いた分析により、初期の層で高頻度トークンが優勢であること、そしてその後の層で大幅な洗練が行われることが定量的に示されました。
LogitLensとの比較:なぜTunedLensが重要なのか
従来のLLM分析ツールであるLogitLensでは、初期層における高頻度トークンの優位性は確認されませんでした。これは、LogitLensが初期層の表現を正確にデコードできない可能性を示唆しています。一方、TunedLensは、より忠実度の高いデコードを可能にするため、初期層におけるLLMの「推測」をより正確に捉えることができるのです。
“Guess-then-Refine”フレームワークは、LLMの予測プロセスを理解するための強力なレンズを提供します。LLMは、初期段階での統計的な推測から、文脈理解に基づく洗練へと、段階的に予測を改善していくのです。この戦略を理解することは、より効率的で高性能なLLMの開発に繋がるでしょう。
事例研究1:品詞による深さの使い分け
LLM(大規模言語モデル)が文を理解し、予測を行う際、すべての単語を同じように扱っているわけではありません。このセクションでは、LLMが品詞の種類に応じて、異なる「深さ」、つまりネットワークの層を使い分けていることを解説します。具体的には、機能語と内容語という2つのグループに分け、それぞれがLLM内でどのように処理されるかを見ていきましょう。
機能語と内容語:役割の違い
まず、機能語と内容語の違いを確認しておきましょう。
- 機能語:文の構造を支える役割を持ちます。例えば、冠詞(a, the)、前置詞(in, on, at)、助動詞(can, will, must)などが該当します。これらは文法的な意味合いが強く、具体的な意味を持つわけではありません。
- 内容語:文の主要な意味を担う役割を持ちます。例えば、名詞(cat, book)、動詞(run, read)、形容詞(beautiful, interesting)などが該当します。これらは具体的な対象や行動、性質などを表します。
LLMは、これらの異なる役割を持つ単語を、ネットワークのどの層で処理しているのでしょうか?
機能語は浅い層で、内容語は深い層で処理される
論文「How Do LLMs Use Their Depth?」の研究チームは、LLMが次の単語を予測する際に、各単語がネットワークのどの層で「トップランク」になるかを分析しました。「トップランク」とは、LLMが最も可能性が高いと判断した単語が、実際に予測されるべき単語と一致することを意味します。
分析の結果、機能語は比較的浅い層でトップランクになる傾向があることがわかりました。つまり、LLMは早い段階で「次にどんな文法的な要素が必要か」を判断できるということです。一方、内容語がトップランクになるには、より深い層での処理が必要でした。これは、LLMが文脈をより深く理解し、具体的な意味を把握する必要があるためと考えられます。
具体例で理解を深める
例えば、次の文章を考えてみましょう。
この文章において、機能語は「The」「on」「the」であり、内容語は「cat」「sat」「mat」です。LLMは、比較的早い段階で「The」や「on」といった単語を予測できますが、「cat」「sat」「mat」といった単語を正確に予測するには、文章全体の文脈を理解する必要があるため、より深い層での処理が必要となるのです。
SpacyとTunedLensの活用
この研究では、Spacyという自然言語処理ライブラリを使って単語の品詞を特定し、TunedLensというツールを使って、LLMの各層における単語の予測ランクを追跡しました。これらのツールを使うことで、LLMの内部で何が起こっているのかをより詳細に分析することが可能になったのです。
この発見から何がわかるのか?
LLMが品詞によって層を使い分けているということは、LLMが文を理解するプロセスが、単なる単語の羅列の処理ではなく、文法構造と意味内容の両方を考慮した複雑な処理であることを示唆しています。この知識は、LLMの効率的な学習方法や、特定のタスクに特化したLLMの設計に役立つ可能性があります。
次のステップ
次のセクションでは、LLMが複数の単語からなる事実を想起する際に、どのように層を使い分けているのかを解説します。お楽しみに!
事例研究2:事実想起における多段階予測
大規模言語モデル(LLM)がどのように深さを利用して事実を想起するのかを探るため、本節では多段階の事実想起タスクに焦点を当てます。これは、モデルに事実に関する質問をし、その答えが複数のトークンに及ぶ場合を分析するものです。例えば、「自由の女神像はどこにありますか?」という質問に対し、モデルは「ニューヨークシティ」と答えなければなりません。このタスクにおいて、LLMは各トークンを予測するためにどれだけの「深さ」、つまりネットワークの層を必要とするのでしょうか?
多段階の事実想起タスクとは?
多段階の事実想起タスクでは、モデルは複数のステップを経て答えを生成する必要があります。このプロセスを理解するために、MQUAKEデータセットを用いて分析を行います。MQUAKEデータセットには、単一トークンで完結する事実だけでなく、複数トークン(例えば「ニューヨークシティ」)を必要とする事実も含まれています。重要な点として、ここではモデルが正しい答えを生成するシナリオに限定して、内部計算を調査します。不正解の場合を分析に含めると、また別の要因が絡み、LLMの深さ利用の実態が見えにくくなるためです。
最初のトークンが最も重要
分析の結果、答えの最初のトークンは、残りのトークンよりも多くの計算深度を必要とすることがわかりました。つまり、「ニューヨークシティ」という答えを生成する場合、「ニューヨーク」を予測する際に、最も深い層まで情報が伝播している必要があるのです。これは、LLMが質問を理解し、正しい文脈で答え始めるために、より多くの計算を必要とすることを示唆しています。
以降のトークンは浅い層で予測可能に
興味深いことに、2番目と3番目の回答トークン(「ヨーク」、「シティ」)の予測は、最初よりも早く出現することが確認されました。これは、最初のトークンが文脈を確立し、以降のトークンがより予測しやすくなるためと考えられます。一度「ニューヨーク」という地名の一部であると認識されれば、「シティ」は比較的容易に予測できるでしょう。
事実の難易度と必要な深さ
また、事実の想起は、事例研究1で扱った機能語(冠詞や前置詞など)の生成ほど簡単ではないことも重要です。事実を正確に思い出すには、より多くの層を通過し、より複雑な計算を行う必要があるのです。さらに、複数トークンの事実を思い出すことは、モデルが将来のトークンを予測する必要があるため、単一トークンの事実を思い出すよりも困難です。これは、LLMがルックアヘッド、つまり先読みのようなメカニズムを備えている可能性を示唆しています。将来のトークンを予測することで、より正確な事実想起を可能にしているのかもしれません。
まとめ
この事例研究から、LLMは多段階の事実想起タスクにおいて、最初のトークンを予測するために最も深い層を利用し、以降のトークンはより浅い層で予測するという、効率的な計算戦略を採用していることが示唆されました。これは、LLMがタスクの複雑さに応じて、柔軟に深さを使い分けていることの証左と言えるでしょう。
事例研究3:選択肢タスクでの推論プロセス
大規模言語モデル(LLM)は、複雑な問題を解決するために、その深さをどのように活用しているのでしょうか。本セクションでは、選択肢が限られたタスクにおけるLLMの推論プロセスを詳細に分析します。具体的には、多肢選択式(MCQ)やTrue/False形式の質問応答タスクを例に、LLMがどのように層を使い分け、効率的に正解を導き出すのかを解説します。
二段階の予測パターン
選択肢が限られたタスクにおいて、LLMは特徴的な二段階の予測パターンを示すことが明らかになりました。
- 初期の層での選択肢の絞り込み:LLMは、初期の層を活用して、与えられた選択肢の中から有効なものを絞り込みます。これらの有効な選択肢は、中間層のlogitにおいてトップランク内に集められます。
- 後の層での推論と最終判断:初期の層で絞り込まれた有効な選択肢に対し、LLMは後の層で詳細な推論を行います。そして、どの選択肢が最も適切かを判断し、最終的な答えを生成します。
この二段階の予測パターンは、タスクの種類に関わらず共通して見られる現象であり、LLMが効率的に推論を行うための重要な戦略であると考えられます。
複雑さ認識深度の使用 (Complexity-Aware Depth Use)
興味深いことに、LLMが各段階にどれだけの「深さ」を使用するかは、タスクの複雑さに依存することが示唆されています。より簡単なタスク、例えば機能語(冠詞や前置詞など)の予測や、選択肢タスクでの有効な選択肢の識別などは、比較的浅い層で実行されます。一方、内容語(名詞や動詞など)の予測、事実の想起、そして選択肢間の推論といったより複雑な処理には、LLMはより深い層を活用します。
この観察は、LLMがその計算資源を最適化し、タスクの難易度に応じて必要な深さを動的に調整していることを示唆しています。これは、LLMが単なるブラックボックスではなく、高度な知能を持つシステムであることを示唆する証拠と言えるでしょう。
データセット
本研究では、以下の著名なデータセットを用いて実験を行いました。
- MMLU (Massive Multitask Language Understanding):様々な科目の知識を問う多肢選択式問題
- Sentiment Analysis (SST):映画レビューの感情分析
- Natural Language Inference (NLI):前提文と仮説文の関係推論
- Paraphrase Detection (MRPC):二つの文が互いに言い換えになっているかの判定
これらのデータセットを用いることで、様々なタスクにおけるLLMの深さの使い分けを詳細に評価することができました。
TunedLensの検証:予測の信頼性
TunedLensプローブの有効性
これまでの分析では、TunedLensを用いることで、LLM初期層において高頻度トークンが上位予測を支配する傾向が見られました。しかし、この傾向がTunedLens自体のバイアスによるものなのか、それともLLMの内部表現を反映したものなのかを検証する必要があります。
この疑問を解消するため、以下の検証を行います。
- 高頻度トークンの確率の比較:TunedLensの各層における高頻度トークンの出現確率を、最終LLM層における確率と比較します。もしTunedLensが特定種類のトークンに偏った確率を割り当てている場合、初期層と最終層で確率分布に大きな乖離が見られるはずです。
- 更新頻度の調整:高頻度トークンの学習頻度を意図的に抑制したカスタムTunedLensをトレーニングします。これにより、学習バイアスが結果に与える影響を評価できます。
検証結果
実験の結果、コーパス内で最も頻繁に出現するトークン(例えば”the”など)の更新頻度を大幅に(1/1000に)削減しても、初期層のトップ1予測として、そのトークンが依然として高い頻度で出現することが確認されました。
このことは、LLM初期層における高頻度トークンの支配的な出現が、プローブのバイアスによるものではなく、むしろ初期層の内部表現に内在する情報内容を反映していることを強く示唆しています。言い換えれば、LLMは初期段階で、文脈情報を十分に考慮できない状況下において、統計的な確率に基づいて”推測”を行っていると考えられるのです。
まとめ:LLMの深層学習戦略を理解する
LLM(大規模言語モデル)がどのようにその「深さ」、つまり多層構造を利用して予測を行うのかを解説してきました。重要なポイントは、LLMが初期段階で統計的な推測を行い、文脈情報が蓄積されるにつれてそれらの推測を洗練する、という点です。
LLMは、タスクに応じて深さを柔軟に利用します。例えば、機能語(助詞や接続詞など)の予測や、選択肢が限られたタスクでの有効な選択肢の識別といった比較的簡単なタスクは、初期の層で処理されます。一方、内容語(名詞や動詞など)の予測、事実の想起、複雑な推論といったタスクには、より深い層が使用されます。
このようなLLMの深層学習戦略を理解することは、より効率的なLLM開発に不可欠です。モデルがどの層でどのような処理を行っているのかを把握することで、計算資源を最適化し、より高速で正確なLLMを構築できる可能性があります。今後の研究では、この知見を活かし、LLMの潜在能力を最大限に引き出すための様々な手法が開発されることが期待されます。
今後は、今回の記事で得られた知見を活かし、LLMの計算効率を改善するための研究が進むでしょう。例えば、タスクに応じて必要な層だけを動的に利用する動的深度モデルや、初期の推測の精度を高めるための事前学習戦略などが考えられます。
参照:
- Akshat Gupta, Jay Yeung, Gopala Anumanchipalli, Anna Ivanova. How Do LLMs Use Their Depth?. arXiv preprint arXiv:2510.18871v1, 2025.

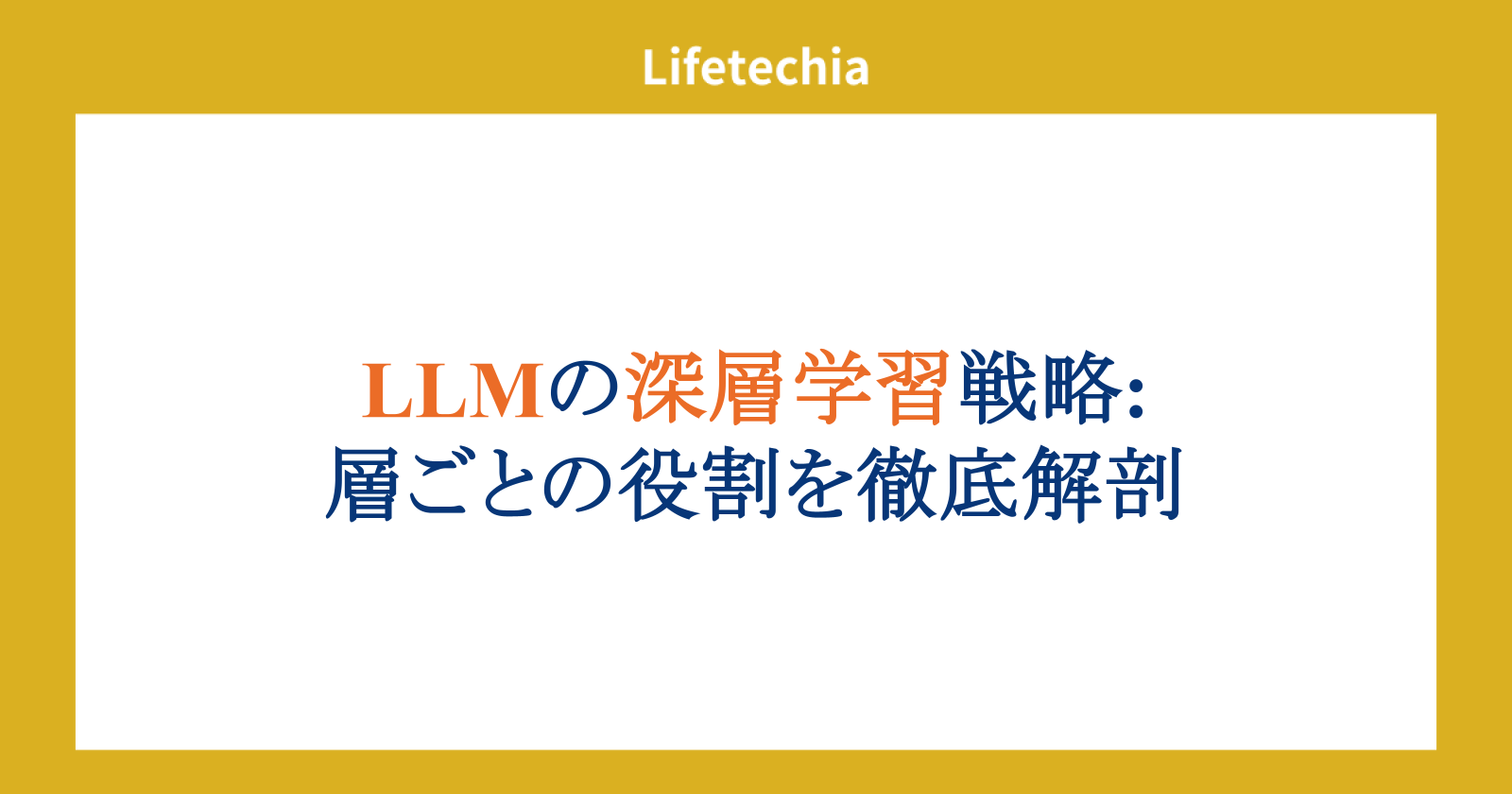
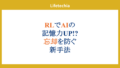

コメント